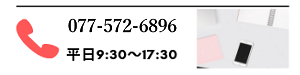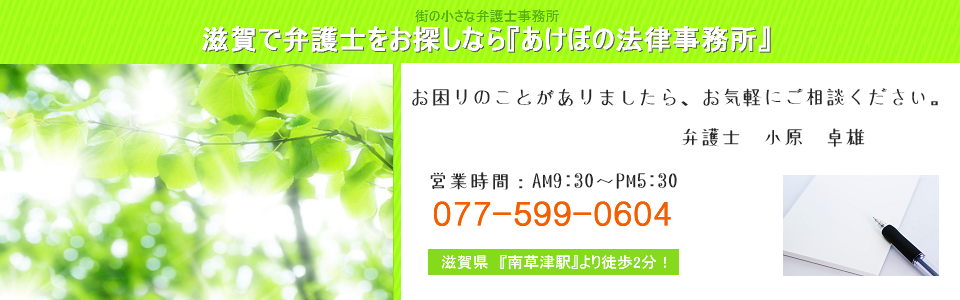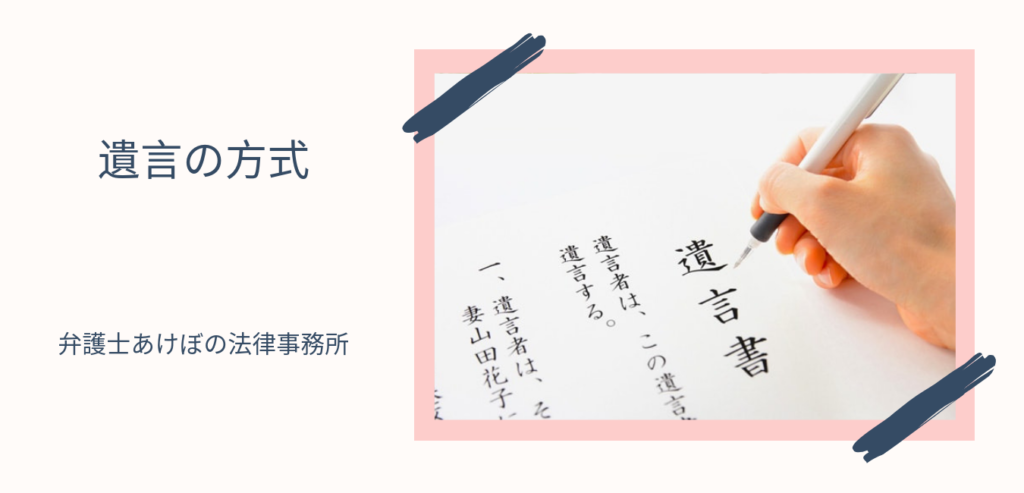弁護士あけぼの法律事務所の目次
事務所関連
- 出張相談はできますか?
- 身体が不自由で外出が困難な場合などには出張相談もできますので、遠慮なくご相談ください。
- 弁護士費用の分割払いは可能ですか?
- 弁護士費用には着手金と成功報酬があります。 着手金は、契約時に一括払いが基本ですが、経済的事情によっては分割払いも可能です。 成功報酬の支払時期は、事件の終了時とする場合や実際に相手方から支払を受けた時とする場合などがあり、また分割払いも可能です。
離婚と調停
- 離婚するには調停が必要なのですか?
- 協議離婚ができないときは、原則として調停が必要です。 すぐに裁判を起こしても、調停に回されます(例外はあります。)。
- 子どもの親権でもめたときはどうすればよいのですか?
- 調停か裁判で決めることになります。
- 子どもの親権を決める基準は何ですか?
- 子どもがどちらを慕っているかが大事です。 いままでどちらが育ててきたか、育て方はどうだったか、子どもは健やかに育っているかなども大切です。 経済的な能力だけで決めるものではありません。
別居と生活費
- 別居後生活費をもらえないときはどうすればよいのでしょうか?
- 一方的に生活費を打ち切られたり、不当に減額されたときは、婚姻費用分担の調停や審判を申し立てることができます。 申立てをすれば、相手方が拒否しても、裁判所が必ず必要額を決めてくれます。
遺言
- 条件を付けた遺言はできますか?
- 例えば、障害を抱えた子の面倒を見てくれるという信頼できる人に、その子の面倒を見てもらう代わりに、財産を遺贈したいと思われる場合などが考えられます。 これを法律上「負担付遺贈」といいますが、負担付遺贈をする場合に配慮すべきことは、負担の内容を明確にすることと、その負担が、遺贈の目的の価額の範囲内にあるようにすることですが、このような遺言をする場合には、受遺者となるべき人と、事前に十分話し合っておくことが必要と思われます。 遺言が効力を生じた後に、受遺者が負担した義務を履行しない場合には、相続人は、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができることになっています。
- 先に妻が亡くなった場合は、どうなりますか?
- 妻に全部を相続させるとした内容の遺言を作成した後、遺言者より先に亡くなってしまった場合、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば、「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、誰々に相続させる。」と決めておけばよいわけです。これを「予備的遺言」といいます。
- 亡くなった人が遺言を残しているかどうかは調べられますか?
- 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理されていますので、すぐに調べることができます。秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっています。
相続と遺産分割
- 相続放棄に期限はありますか?
- あります。 原則として相続を知ったときから3か月以内です。 放棄するかどうか迷うときは、期限を延長してもらうこともできます。期限後に多額の債務が出てきたときなど例外的な場合には、3か月経過後でも相続放棄が認められる場合があります。
- 相続と遺産分割は違うのですか?
- 少し違います。 相続は、遺産(借金も含めて)がすべて相続人(全員)に移転することです。 遺産分割は、遺産のうちどれを誰がもらうかを決めるものです。
- 遺産分割はいつまでにしなければなりませんか?
- 期間の制限はありません。 どんなに遅くなってもすることができます。 祖父母の遺産分割ができていないことはよくあります。
交通事故
- 示談成立後に後遺障害が出てきた場合、さらに損害賠償を請求できますか?
- できます。示談当時に予測できなかった後遺障害が後に出現したときは、示談の効力は後遺障害にまでは及ばないため、新たに損害賠償を請求できます。